地域経済とバイオマス発電の関係性!地方創生の新たな鍵に!
- 2025.09.23
- バイオマス発電

日本経済における問題のひとつが、東京一極集中と言われています。
人口移動の多い東京に産業が集まることで地方における人口流出は避けられない状況であり、近い将来地方経済がさらに厳しい状況に追い込まれることは確実です。
そんな中、地方経済の発展、地方創生の新たな鍵として注目されているのが、「バイオマス発電」と言われています。
本記事では、バイオマス発電が、なぜ地方経済を救う鍵になるのか解説していきましょう。
バイオマス発電について

バイオマス発電は、太陽光発電や風力発電、水力発電と同じ再生可能エネルギーのひとつです。
バイオマスとは、生物資源を意味するバイオと量を意味するマスをかけ合わせた言葉であり、化石資源を除く再生可能な有機性資源を使用した発電が、「バイオマス発電」と呼ばれています。
バイオマス発電の特徴が、下記燃料を利用して発電されているところです。
| 木質バイオマス(木質燃料) | 間伐材、製材工場残材、建築廃材などを利用 |
| 廃棄物系バイオマ(バイオガス) | 生ごみ、食品加工残渣、汚水・汚泥などを利用 |
また、これらさまざまな資源を発電するために下記3つの方式が存在します。
| 直接燃焼方式 | 木材や可燃ゴミ、廃油などをボイラーで燃焼させる方式。主に発電効率の観点から大規模な設備で用いられている。 |
| 熱分解ガス化方式 | 資源を高温で熱処理、ガス化することで発電させる方式。燃焼温度が高く、小規模設備でもある程度の発電効率を得ることができる。 |
| 生物化学的ガス化方式 | 生ゴミ、汚泥、家畜の糞尿などを発酵させ、ガス化し発電する方式。廃棄物系のバイオマスに用いられており、発電効率も高い。 |
再生可能な有機性資源を利用するバイオマス発電は効率的かつCO2を排出しない地球環境を守る発電方式と注目されており、近年日本でも各地で発電所が建設されるようになりました。
数ある再生可能エネルギーの中でもシェア率が高まっており、今こそこのバイオマス発電所を地方に建設することで地方創生の鍵となると考えられています。
バイオマス発電所の建設場所
バイオマス発電は、発電所を建設する場所に特徴があります。
上記でもお伝えしたようにバイオマス発電には、木質バイオマス(木質燃料)と廃棄物系バイオマス(バイオガス)が存在していますが、そのほかにも黒液・廃材、セルロース(古紙)、生活から出る産業食用油などもバイオマスとして利用することが可能です。
これらさまざまなバイオマスが資源となるだけに、廃棄されるバイオマスに合わせた場所に発電所を建設する必要があります。
例えば、木質バイオマス(木質燃料)を資源とするバイオマス発電所を都内に建設するか、郊外または山のふもとで建設するかによって収集費用、運搬費用、管理費用が多く変わってくることは必然でしょう。
そのため、現在日本国内では山林や牧場に近い場所、廃棄物処理施設の内部などにバイオマス発電所が建設されており、その結果バイオマス発電所は、“地方”に点在しているのです。
バイオマス発電所と地方創生について
バイオマス発電所は、地方創生の鍵になると期待されています。
そもそも地方創生とは何か、バイオマス発電がその鍵を握っている理由について下記で解説していきましょう。
地方創生とバイオマス

地方創生とは、地域の持続的な発展を目指しながら地域内の人々が土地で暮らし、働き、育てることができる社会を創り上げると定義されるものです。
地方創生には3つの視点に基づく具体的な取り組みがあり、バイオマスは下記のグリーンに関連してきます。
| ヒューマン | 地方へ人の流れを創出する、人材支援など |
| デジタル | 地方創生に資するDXなどの推進 |
| グリーン | 地域が牽引する脱炭素社会の実現 |
バイオマス発電はCO2を排出しない再生可能エネルギーであり、地域が牽引する脱炭素社会の実現、つまり地方創生の脱炭素の好循環に向けた取り組みとして大きな期待が寄せられています。
例えば、地方創生におけるバイオマス発電の役割として下記内容が考えられるでしょう。
・埋もれていた地域資源を活用したバイオマス発電の導入
・バイオマス発電事業を基盤としたサービスの創出・拡大
・バイオマス発電に関連した雇用創出、地方への人の流れ、地域課題の解決
バイオマス発電は地域の資源を活用した再生可能エネルギーとなれば、エネルギーの地産地消へと繋がります。
さらに地方に発電所ができれば雇用を生み出せるだけでなく、その周辺や関連した事業や商業が生まれさらなる雇用創出にもつながるのです。
また、地方創生のポイントとして2013年には経済産業省・農林水産省・7府省などが連携してスタートさせた、「バイオマス産業都市」の取り組みも注目すべきでしょう。
農林水産省では、「バイオマス産業都市」を、「地域に存在するバイオマスを原料に、収集・運搬、製造、利用までの経済性が確保された一貫システムを構築でき、さらに地域のバイオマスを活用した産業創出と地域循環型のエネルギーの強化により地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち、むらづくりを目指す地域」と定義しています。
事業者との連携を条件として7府省が認定を行ない、今では平川氏や佐賀市、甲斐市、秦野市、大崎市など全国の100を超える市町村がバイオマス産業都市として認定を受けている状況です。
「バイオマス産業都市」に選出されることにより、バイオマス関連の「助成金」や「補助金」の加点になることなど自治体にとってもメリットが大きく、より地方創生への道が拓ける可能性が高まるでしょう。
上記のことからも、バイオマス発電の発電所を地方に建設することで、地域経済の活性化などさまざまなメリットを享受できると考えられています。
真庭バイオマス発電事業の事例

バイオマス発電が、実際にどのように地域経済に影響を及ぼしたのか、「真庭バイオマス発電事業」の事例を見ていきましょう。
真庭バイオマス発電事業は岡山県真庭市に位置しており、森林資源である木質バイオマス発電のパイオニア的存在であると言われています。
2015年4月に稼動したバイオマス発電所で、すでに大きな経済効果を出していることで有名です。
バイオマス発電の資材となる木質燃料購入は年間13億円にも上り、これらは林業関係者への利益還元として図られています。
また、バイオマス発電は再生エネルギーを利用しているため売電収入が期待でき、年間23億円といった売電収入が見込まれているとのことです。
その利益は雇用、また資材購入による生産業者への還元されるため地域経済への貢献は計り知れません。
もちろん、地球温暖化防止への貢献、さらにバイオマス関連の客数が増加することで真庭市周辺の観光振興にもつながるなど大きな経済効果が期待されます。
バイオマス発電を取り入れることで、どの地方自治体も真庭バイオマス発電事業のような成功を収められるわけではありません。
しかし、都市部への人口流出が止まらならい地方にとってバイオマス発電は、地域創生への鍵になることは間違いないでしょう。
バイオマス発電を取り入れた地方の事例
そのほかの、バイオマス発電を取り入れた地方の事例をいくつか紹介します。
●くずまき高原牧場の木質バイオマス発電施設
岩手県岩手郡葛巻町のくずまき高原牧場では、牛の排泄物を利用したバイオマス発電を行うバイオマス発電所を施設内に建設しています。
生物化学的ガス化方式にてメタンガスを抽出、発生した電力と熱をプラント内で消費するエネルギーの地産地消を実現できている好例です。
●徳山バイオマス発電所
徳山バイオマス発電所は、2014年に閉鎖した山口県周南市の徳山製油所の跡地の一部を利用して建設されたバイオマス発電所です。
出光グループが管理する発電所で、木質ペレット、パーム椰子殻をバイオマスとして発電が行われています。
また、中長期的には国産の間伐材や製材端材等を使用することによる、持続可能な森林づくりと林業振興、さらに地域経済の構築と発展を目指しているとのことです。
●豊橋市 バイオマス利活用センター
豊橋市では、下水を処理する過程で発生してしまう汚泥、地域の生ゴミなどを生物化学的ガス化方式によって発電するための資源として活用しているバイオマス利活用センターがあります。
メタン発酵によりバイオガスを取り出していますが、残った汚泥も炭化燃料に加工するなど無駄のない完全エネルギー化が叶えられています。
●日田市 株式会社グリーン発電大分 木質バイオマス発電所
大分県の日田市では、木くずなどを燃料とするバイオマス発電事業を行う発電所があります。
日田市は木材産業が盛んな地域であり、地域林業者と連携した取り組みが進められています。
さらに発電所の隣接地にある栽培ハウスにて発電所の排温水を安価に活用するなど、バイオマス発電に関連した事業も展開されているところが特徴です。
まとめ
バイオマス発電所は、環境に優しい再生可能エネルギーとしてだけでなく、地域経済を豊かに、地域創生の鍵となる注目の発電方法です。
地域の資源や産業を守り、循環させ、新たな雇用を創出していく今までない発電方法であることは間違いないでしょう。
これからバイオマス発電がどのように広がり、地域経済を動かしていくのか。
長い目で見守り続けましょう。
-
前の記事

バイオマス発電の課題はどこにあるのか?今後についても解説! 2025.04.01
-
次の記事
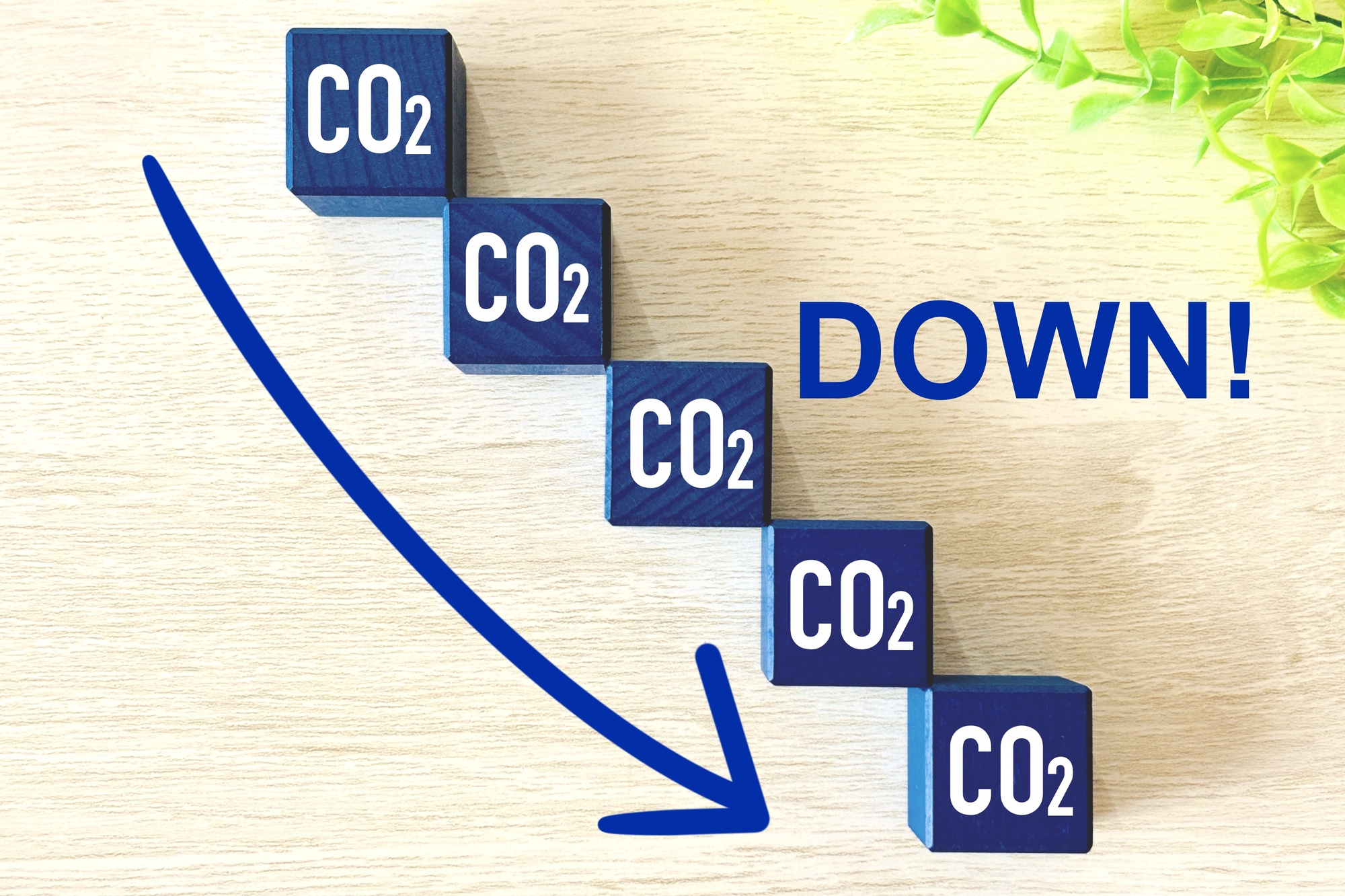
バイオマス発電はCO2削減を実現する発電方法!わかりやすく解説! 2025.09.23