誤解されがちなバイオマス発電!CO2排出とカーボンニュートラルの仕組みを解説!
- 2025.09.24
- バイオマス発電
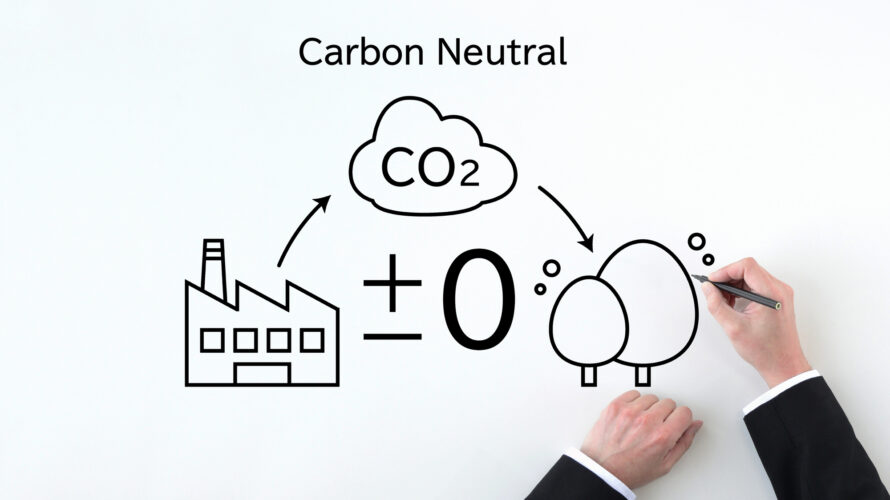
植物や木材、農業廃棄物など食品廃棄物を原料として電力を生成するバイオマス発電。
再生可能エネルギーのひとつとして注目されていますが、発電システム自体に環境負荷が少ないことでも注目されています。
一方、バイオマス発電はカーボンニュートラルではないと誤解されている側面もあり、本来のところはどうなのか気になる方も多いようです。
本記事では、誤解されがちなバイオマスにおける、CO2排出やカーボンニュートラルにおける仕組みを解説していきます。
バイオマス発電とカーボンニュートラル
バイオマス発電が環境負荷の少ない発電方式と言われている理由のひとつに、カーボンニュートラルへ寄与があります。
そもそもカーボンニュートラルとは何か、なぜバイオマス発電がカーボンニュートラルへ寄与するのかあらためて解説していきましょう。
カーボンニュートラルとは何か?

カーボンニュートラルとは、炭素(カーボン)と均衡(ニュートラル)が組み合わさった概念で、具体的には炭素の排出量と吸収を均衡させることを言います。
CO2は地球温暖化の要因のひとつと考えられており、世界的にカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが求められている状況です。
地球温暖化の要因とされている温室効果ガスは、CO2だけではなく、「メタンガス・フロンガス」など、C(炭素)が要因とされています。
中でもCO2は最も影響が大きいと考えられており、一人ひとりが意識しながらCO2排出量を減少させる努力が必要です。
カーボンニュートラルは、排出されているCO2などの温室効果ガスを人為的に吸収、除去して実質的に排出量をゼロにする仕組みになります。
例えば、経済活動などによるCO2が排出されますが、植林や森林管理によって吸収量を差し引いた合計を実質ゼロにするといった取り組みです。
ここでのポイントはカーボンニュートラルはCO2を完全にゼロにするのではなく、実質的な排出量をゼロにするところにあります。
CO2を除去する仕組みを利用しても、完全にゼロはできません。
その残った排出量を森林が自然に吸収することにより、温室効果ガスが実質ゼロになったとみなす取り組みです。
バイオマス発電がカーボンニュートラルと言われる理由

バイオマス発電は、数ある発電方式の中でもカーボンニュートラルに寄与していると言われています。
その理由のとして、バイオマスが廃棄物や植物などを原料としているところが挙げられるでしょう。
・バイオマス発電の原料となる植物などが成長する過程でCO 2が吸収され、燃焼時に排出されたCO2は結果的に成長過程で吸収される量と相殺されるから
・廃棄物を利用するため埋立地でのメタン発生を防げる、化石燃料を使用しないためCO 2排出量を減らせるなど
まず、木質バイオマスを利用するにあたり、樹木の伐採後に森林が更新されることで発電によって排出されたCO2は樹木に吸収されるため実質CO2の排出量をゼロにできます。
また、CO2を削減するだけでなく、排出量を減らす上でもバイオマス発電は寄与していることもポイントです。
上記のように、バイオマス発電は廃棄物を原料とした発電方式であることから、埋立地からのメタン発生を防ぐことができるほか、化石燃料などを使用しないためCO2排出量がそもそも低減できるといったメリットがあります。
カーボンニュートラルに寄与するだけでなく、廃棄物を使用するといった概念からも資源循環型社会の実現に寄与できるところがバイオマス発電の特徴でしょう。
バイオマス発電への誤解
バイオマス発電は、上記のようにカーボンニュートラルに寄与する発電方式です。
さらに木質バイオマスを活用にあたって原料となる森林が更新されることからも、CO2排出量の削減だけでなく資源循環型社会への実現が期待されています。
一方、バイオマス発電はカーボンニュートラルではない、石炭よりも悪い結果を招くといった、“誤解”された情報が広く拡散されている実態もあるようです。
バイオマス発電における誤解について下記で解説していきましょう。
誤解されているポイント
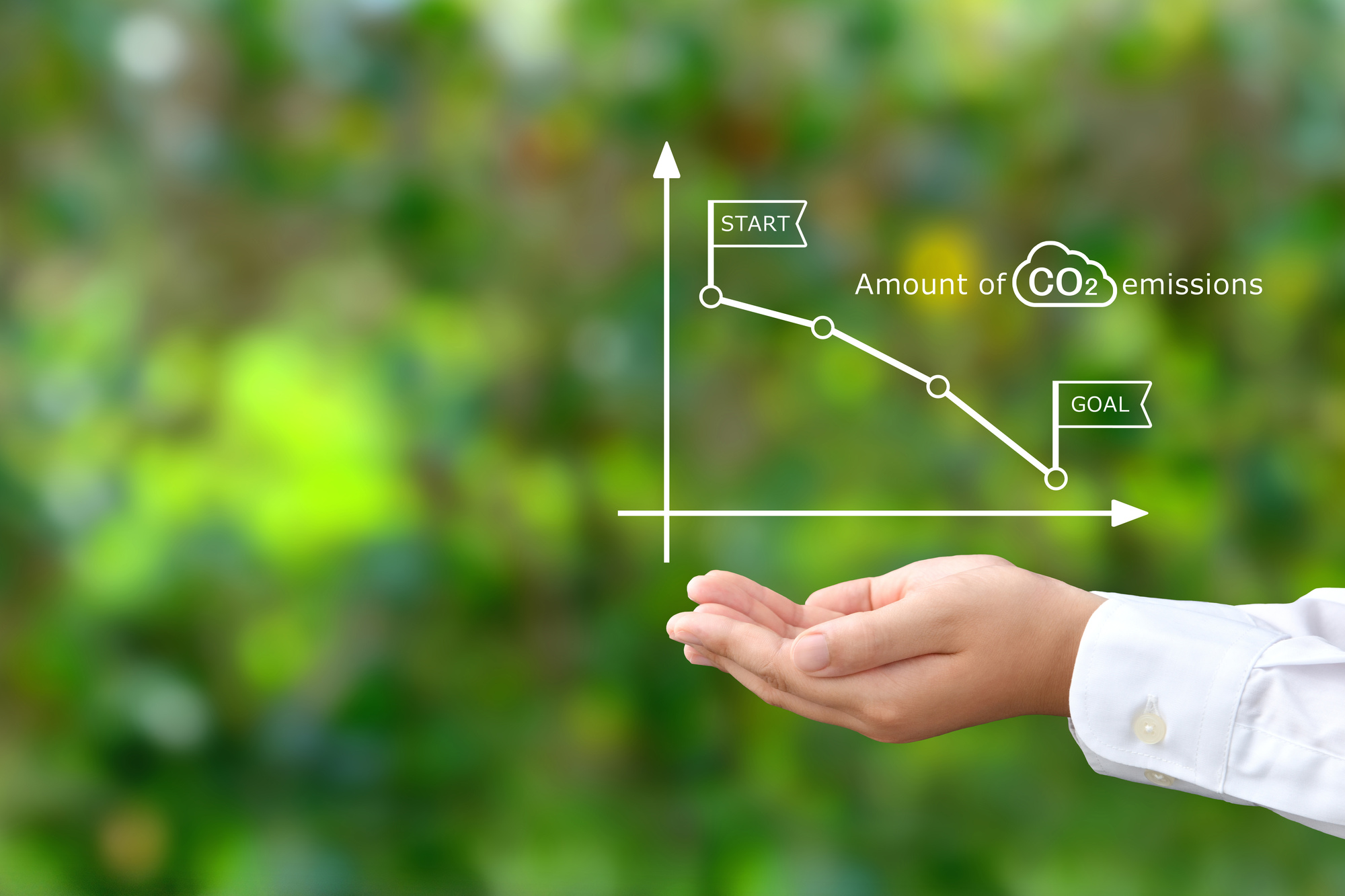
バイオマス発電における原料の燃焼時に排出されるバイオマス由来のCO2は、ゼロとされてきています。
もともと、燃焼時に発生するCO2は植物の光合成によって固定されており、大気中のCO 2濃度は影響を与えないといった考え方です。
IPCCガイドラインにおいて、バイオマスを起源としているCO2は収穫時の炭素蓄積量の変化による排出として農林業部門で計上されることが基本で、エネルギー部門などで計上されません。
しかし、バイオマス発電への論争の中では、バイオマス由来のC02はエネルギー部門の排出として見なしており、結果的に化石燃料よりも排出が多いと指摘されています。
さらに排出されたCO2を吸収するための森林バイオマスにおいては、再吸収に時間を要するため炭素負債が発生していると誤解されているのです。
また、エネルギー利用のために森林を伐採、さらに伐採した木材を燃料として利用することを前提としているため、こういった活動自体で炭素負債が増えるといった誤解もあります。(森林バイオマスの発電所の建設なども含め)
バイオマス発電はカーボンニュートラルが期待できる

バイオマス発電はカーボンニュートラルではないと誤解されている部分もありますが、それらは明確に否定されています。
まず、森林を構成している樹木などは光合成によって大気中の二酸化炭素の吸収・固定を行っており、木材をエネルギーとして燃焼しても、樹木の伐採後に森林が更新されることでいずら吸収されることにつながるでしょう。
そして、木質バイオマス発電の本格化により、森林内に廃棄されていた間伐材などの用途が生まれるわけで森林自体が息を吹き返している事例もあります。
バイオマスの原料とするためだけに森林が伐採されることはあり得ず、基本的には残渣が原料です。
これら残渣が原料となり活用されることで林業関係者における経済活動に寄与し、森林自体が持続可能な資源となっていくことでカーボンニュートラルは実現可能でしょう。
そして、森林伐採と言っても成長量の範囲内での伐採であることで、ほかの森林によりCO2が吸収されるといった期待が持てます。
上記でお伝えしているように、林業など経済的な森林関係の市場環境が実現することで、木材利用料と森林蓄積量のバランスが整い、バイオマス発電におけるカーボンニュートラルが実現できるのではないでしょうか。
また、そもそも化石燃料とバイオマスにおけるCO2の本質的な違いが区別されていないことも誤解を招いている要因です。
まず、燃焼においてエネルギー量当たりのCO2排出量は化石燃料よりバイオマスの方が多くなりますが、バイオマスが酸素原子が多いといった分子組成による違いであり、そこを無視してしまっては議論になりません。
まとめ
バイオマス発電への誤解は今もなお続いていますが、その内容をしっかりと理解し整理することが大切です。
カーボンニュートラルとCO2の仕組みを理解し、バイオマス発電がどのように寄与しているのか、正しい情報を得る必要があります。
バイオマス発電は、木材をはじめ廃棄物を利用できる地球環境に負荷の少ない発電方式です。
バイオマス発電への誤解を解くためにも、一人ひとりが正しい知識を持つ必要があるでしょう。
-
前の記事

バイオマス発電所は進化している!安全対策とモニタリング体制の今を解説! 2025.09.24
-
次の記事

バイオマス発電所の安全対策の今!現場の実態に迫る! 2025.09.24