バイオマス発電所は進化している!安全対策とモニタリング体制の今を解説!
- 2025.09.24
- バイオマス発電

今、注目されている再生可能エネルギーのひとつがバイオマス発電です。
生物資源を燃焼させた際の熱を利用した発電方式で、廃棄物の再利用やカーボンニュートラルの実現、地域創生の鍵になるなどメリットが多いことで知られています。
一方、バイオマス発電所は火災や爆発のリスクがあることで知られており、発電所における安全対策やモニタリング体制の徹底が重要です。
本記事では、バイオマス発電所の安全対策とモニタリング体制についてまとめました。
バイオマス発電所が、どのように安全対策を行っているのか確認してみてください。
バイオマス発電所の火災・爆発リスクについて

バイオマス発電の方式には、「直接燃焼方式・熱分解ガス化方式・生物化学的ガス化方式」といった種類があります。
再利用される資源に違いがありますが、基本的にはバイオマスを燃料とし、その熱で蒸気またはガスを生成させて電気を生み出す仕組みです。
しかし、バイオマスとして利用される木質ペレットや木材チップ、さらに微生物を起因とした火災・爆発リスクは避けることができません。
バイオマス発電所の火災・爆発リスク、また事故の事例について解説していきましょう。
火災・爆発リスク
バイオマス発電所は、火災リスクまたは爆発リスクがあります。
・木質のバイオマスや微生物の酸化により熱が発生する可能性がある。
・蓄熱が進むことで自然発火のリスクが高まる。
・メタンや一酸化炭素など、可燃性ガスが蓄積する。
・静電気や摩擦熱によるもの。
・木粉塵によって粉塵爆発が引き起こされる。
など、実際に、2018年に木質燃料の発酵による発熱があり、それを起因とした大規模火災が発生したことで施設の大部分が焼失したといった事例もあります。
安全面に留意して稼働されている発電所ながら、火災・爆発のリスクは避けることは難しいのです。
事故事例
バイオマス発電所では、過去に複数の火災・爆発事故が発生しています。
| 発電所・発生年 | 事故原因 | その後の対策 |
| 千葉・2023年 | 木質ペレットの自然発火による火災事故 | 再発防止策実施 |
| 山形・2019年 | 水素ガスタンクの爆発事故 | 設計・施工担当社が破産手続開始 |
| 愛知・2024年 | 木質ペレットの粉じん化と摩擦熱による粉じん爆発事故 | 再発防止策実施 |
| 京都・2023年 | 発酵・酸化による発熱。可燃性ガス滞留、自然発火 | 燃料管理方法見直し |
また、中には設備のメンテナンス不備、不適切な燃料混合による火災や爆発といった事例もあります。
これらバイオマス発電所における火災・爆発リスクを下げるためには、徹底した管理体制が必要となるでしょう。
バイオマス発電所の安全対策とモニタリング体制について

バイオマス発電所で使用されるバイオマス燃料に起因する火災などが複数発生していることから、2024年2月1日に経済産業省が「バイオマス発電所における安全確保の徹底及び事故発生時の報告のお願いについて」といった通達を出しました。
その通達において、バイオマス発電設備の設置者には以下3点の対応を徹底することが求められています。
| ① | バイオマス燃料となる木質ペレットは生産地等により品質が必ずしも均一ではない。 そのことから、それぞれの特性を十分に把握した上で、特性に応じた設備面での安全対策が講じられていることを確認。 さらに、貯蔵・運搬設備等、過去に事故が発生している設備、事故の未然防止において必要と考えられる設備に巡視・点検や清掃等など必要な対策を講じること。 |
|
② |
バイオマス燃料に起因する可能性のある火災などが発生した際、電気関係報告規則の報告対象となる事故でなくてもバイオマス発電所を管轄する産業保安監督部に対し、前広に事故の報告を行うこと。 |
| ③ | 2の報告を行う設置者は、当該事故原因究明及び再発防止策についてその検討中の段階から、業界団体等を通じて随時情報の横展開を図ること。今後の類似の事故の発生の未然防止に協力すること。 |
燃料の品質は生産地により大きく異なることから、特性に合わせた安全対策を行うことが重要です。過去事故があった設備はもちろん、新規設備であっても巡視や点検、清掃は徹底して行わなければなりません。
また、法令上報告対象外の火災などの事故であったとしても速やかに管轄の産業保安監督部へ報告することで、早期対応や情報共有につながります。
そして、その報告の原因究明を行うこと、再発防止策を業界団体を通じて共有することで類似事故の発生を防止する必要があるといった通達です。
バイオマス発電は火災・爆発リスクのある発電方式であること、実際に複数の事故が発生していることも忘れてはなりません。
安全性、そして透明性をより重視することが、今後のバイオマス発電所には求められているのです。
バイオマス発電所のモニタリング体制
バイオマス発電所における火災などの事故において、安全対策の徹底は急務です。
定期的なリスク評価の実施や作業者教育の強化、緊急対応計画の策定なども重要ですが、近年最新のモニタリング技術を導入している発電所も増加傾向にあります。
最新のバイオマス発電所のモニタリング体制について解説していきましょう。
IoTセンサーやAIの活用

IoTは、「モノのインターネット」と呼ばれているもので、さまざまなモノがインターネットにつながる仕組みを意味しています。
近年、一部のバイオマス発電所では IoTセンサーによるリアルタイム監視を導入し、24時間の監視体制を整えています。
モニタリングするだけでなく、温度、湿度、ガス濃度などデータがリアルタイムで取得できるため、異常発生時に即座に対応可能です。
とくに木質燃料が発酵する際、温度上昇による火災リスクが高まるため、温度センサーなどのモニタリング体制は必至と考えられるでしょう。
また、Iotと合わせてAIの活用も進んでいます。
AIを活用したデータ分析を利用することで、異常パターンなどを即座に予測できるといったメリットがあります。
ドローン
さまざまな分野で活躍しているドローンですが、バイオマス発電所における安全管理でも活躍しています。
ドローンは高所や危険な場所、立ち入ることが困難な場所を点検することができる装置です。
設備劣化、異常値が出ている場所を素早く点検できるため事故発生リスクを減らすことができます。
窒素ガス発生装置
火災防止に役立つ装置のひとつが、窒素ガス発生装置です。
例えば、燃料の保管環境を不活性ガスである窒素を充満させた空間を意味する、窒素雰囲気にすることにより酸素濃度が下がり発火リスクを低減させることができます。
木質燃料は長期保管されることがあるため、窒素ガス発生装置を導入することにより、画期的に火災リスクを減少されることができるでしょう。
上記のような最新のモニタリング体制を整えることにより、バイオマス発電所での火災や爆発リスクが抑えられ、安全な再生可能エネルギーとして活用が広がるはずです。
もちろん、最も重要なことはこれらモニタリング体制を整えながら、過去の事例を徹底して研究し対策を講じること、従業員全体の定期的なトレーニングと教育は必須でしょう。
マンパワーと最新技術を組み合わせた、徹底した安全対策によりバイオマス発電は安全な設備へと進化していくのです。
まとめ
バイオマス発電所では、資源となるバイオマスによって火災や爆発のリスクを抱えています。
そのため、連続温度モニタリングや早期異常検知、アラート・通知機能など安全対策やモニタリング体制を徹底する必要があるでしょう。
今、最新技術を導入するバイオマス発電所も増えており、さまざまな情報も提供されているため透明性も高まってきています。
より安全で地球に優しい発電方式として、バイオマス発電が認められる日もそう遠くはないのではないでしょうか。
-
前の記事
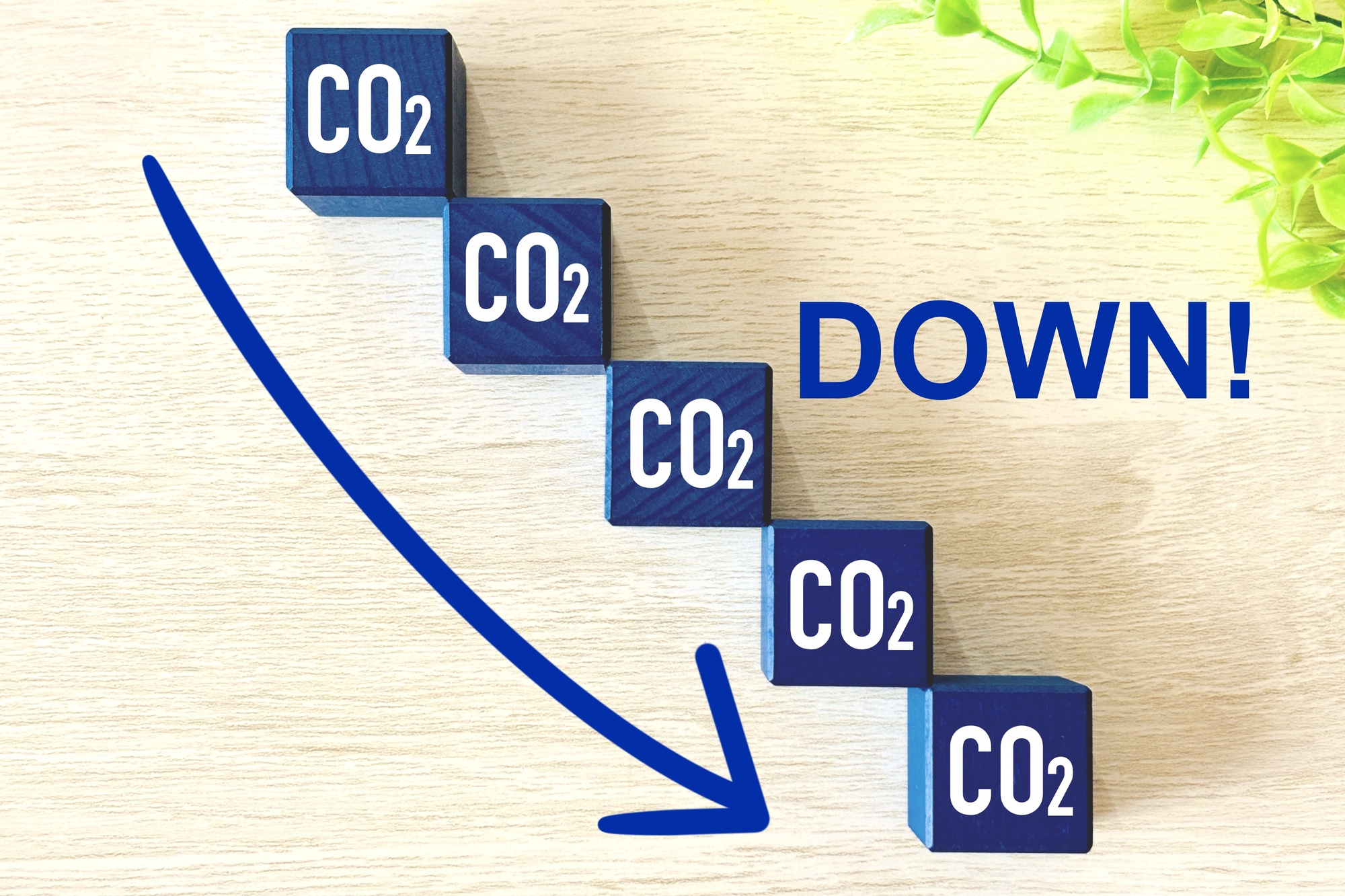
バイオマス発電はCO2削減を実現する発電方法!わかりやすく解説! 2025.09.23
-
次の記事
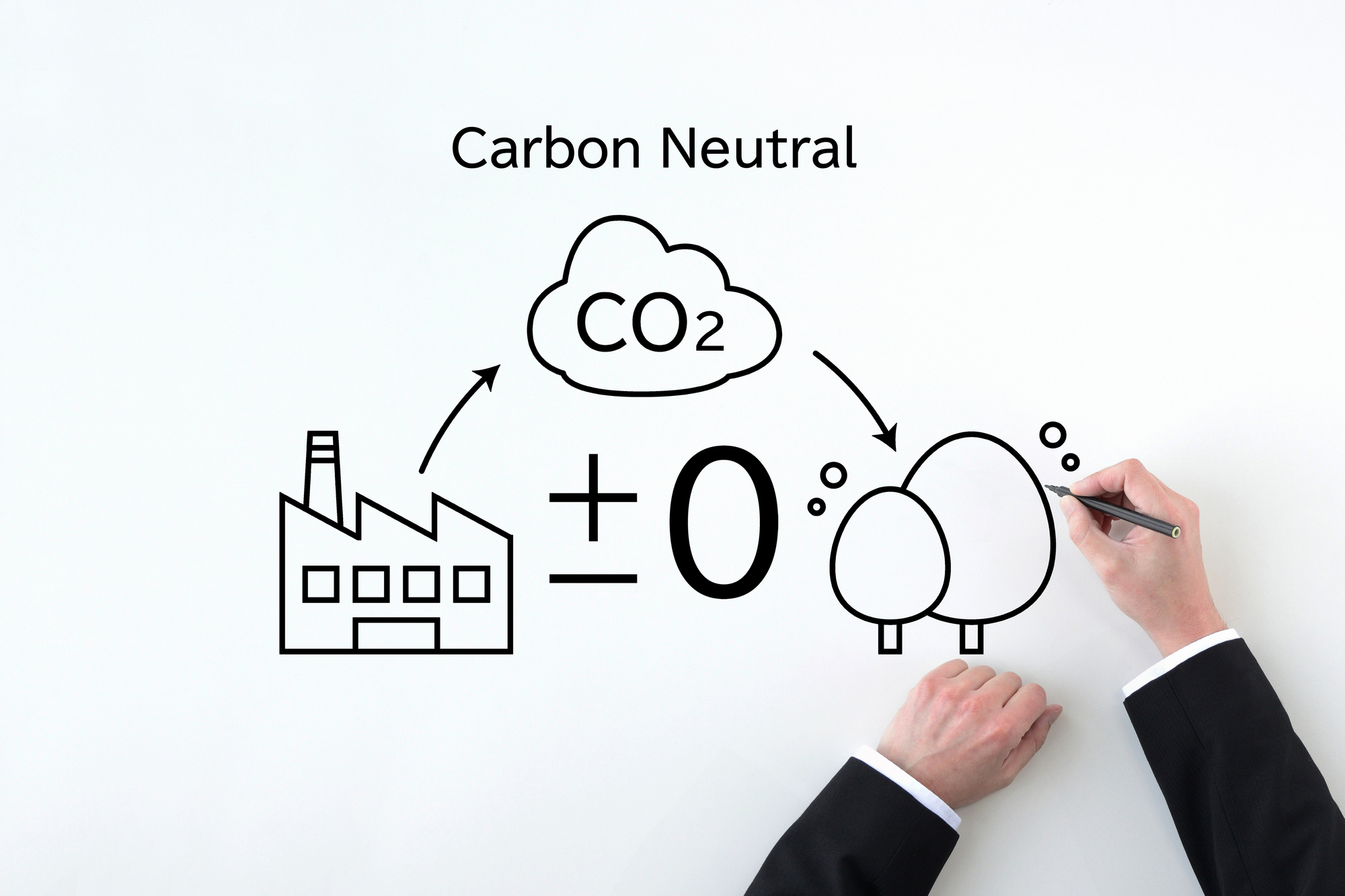
誤解されがちなバイオマス発電!CO2排出とカーボンニュートラルの仕組みを解説! 2025.09.24