バイオマス発電はCO2削減を実現する発電方法!わかりやすく解説!
- 2025.09.23
- BIOMASS TODAY
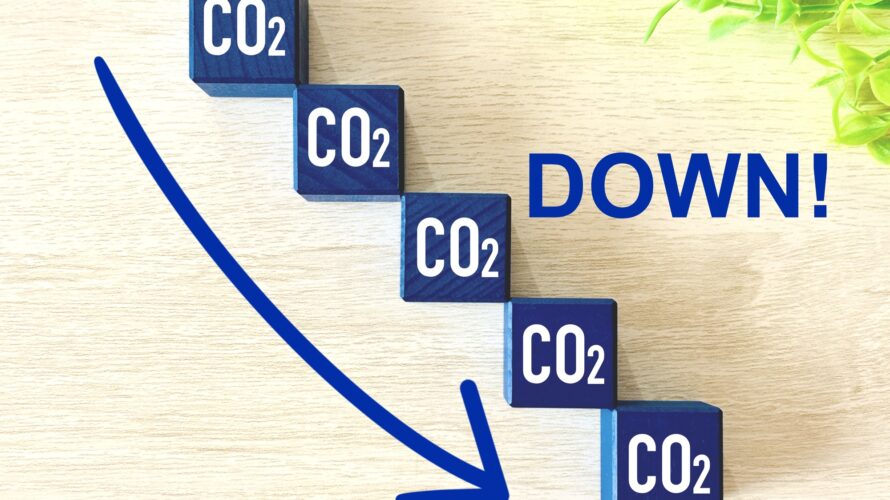
今、日本で注目されている再生可能エネルギーのひとつが、「バイオマス発電」です。
バイオマスとは化石燃料を除く再生可能な生物由来の有機性資源と定義されるもので、バイオマス発電は森林資源や食品廃棄物、家畜排泄物などを資源とする発電方法になります。
バイオマス発電が注目されている理由はいくつかありますが、そのひとつがCO2削減効果が高いといったポイントです。
今話題のカーボンニュートラルを実現させるバイオマス発電とCO2削減の関係性について解説していきましょう。
バイオマス発電のメリットのひとつがCO2削減
バイオマス発電は、バイオマスと呼ばれる再生可能な生物由来の有機性資源を使った発電方式です。
バイオマス発電に使用されるものは大きく分けて下記の3つなります。
| 廃棄物系 | 家畜排せつ物、廃棄紙、下水汚泥など |
| 未利用バイオマス | 麦わら、もみがら、林地残材など |
| 資源作物 | でんぷん資源、糖質資源、油脂資源など |
また上記のバイオマスは、乾燥系や湿潤系、そのほかといった3種類に分けられ、それぞれ発電方式が違います。
| 直接燃焼方式 | 木材や可燃ゴミ、廃油などをボイラーで燃焼させる方式 |
| 熱分解ガス化方式 | 資源を高温で熱処理、ガス化することで発電させる方式。 |
| 生物化学的ガス化方式 | 生ゴミ、汚泥、家畜の糞尿などを発酵させ、ガス化し発電する方式 |
今、バイオマス発電が日本で普及し始めています。
その背景にあるのが、下記のメリットです。
CO2削減効果が期待できる
発電の燃料となるバイオマスは成長過程で光合成により大気中のCO2を吸収している。発電過程においてCO2が排出されるがバイオマスが吸収したCO 2と相殺されるため、CO 2を増やすことはない。
循環型社会の実現
植物などの廃棄物を燃料としているため、資源の無駄遣いにならない。廃棄物は再利用されなければ廃棄場所の確保、廃棄コストが発生して非経済的。バイオマス発電により、それら無駄を削減するだけでなく電気を生み出すため循環型社会の実現につながる。
熱利用可能
バイオマス発電はガス化発電が可能。発電で発生した熱を利用できるため無駄のないシステムとして注目されている。
地域創生につながる
バイオマス発電所を建設することで新しい雇用を生み出すなど、地域経済の活性化につながる。都市部への人口流出を抑え、人材の流入を促す地域創生を叶えると期待されている。
とくにバイオマス発電が注目されているのはCO2削減効果が期待されている、つまりカーボンニュートラルの考え方に基づく発電方法といったメリットです。
カーボンニュートラルとは
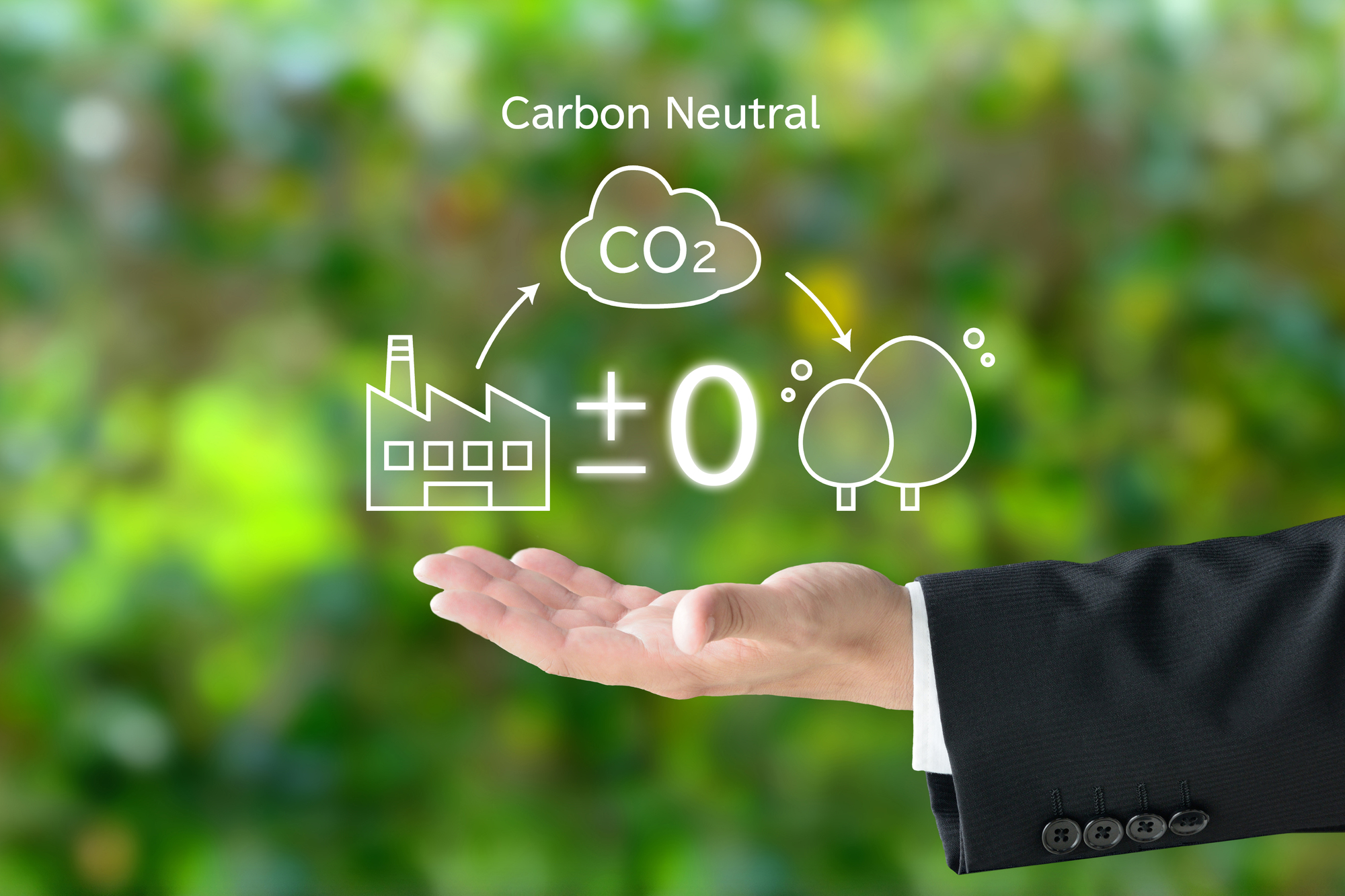
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスを全体としてゼロにする考え方です。
カーボンニュートラルには下記が含まれます。
・CO2
・メタン
・N2O
・フロンガスを含む「温室効果ガス」など
日本では、2050年までに「カーボンニュートラル」を目指すことが宣言されており、国内でそれを目指したさまざまな取り組みが行われています。
できる限りCO2を排出しない仕組みをつくることはもちろんですが、排出せざるを得ない場合でもその量が吸収、除去されることで差し引きゼロといった考え方がカーボンニュートラルの原理です。
発電部門の取り組みがポイント
日本におけるCO2排出量の40%は発電部門が占めており、同部門では脱炭素化技術によるCO2排出量の減少などカーボンニュートラルに向けた取り組みが急務となっています。
現在、代表的な脱炭素技術となる発電方法がこちらです。
・再エネ
・原子力
・火力+CCUS/カーボンリサイクル
・水素発電
・アンモニア発電
中には未だ技術が開発段階にあり安定的に電力が供給できる段階ではないものもありますが、バイオマス発電は再エネ技術としてすでに機能しており、今後がより期待されています。
バイオマス発電がカーボンニュートラルを実現できる理由

上記でお伝えしているように、バイオマス発電はカーボンニュートラルの実現が期待されている発電方法です。
まず、バイオマス発電の燃料となる資源となる材木などの自然由来のものは、成長過程でCO2を吸収しています。
これらバイオマスを燃やした際にCO2が排出されてしまいますが、もともと大気中に存在していたCO2が戻るだけであり、結果的にCO2はプラスマイナスゼロと考えることができるのです。
またバイオマスの定義として、化石燃料は資源となりません。
化石燃料は大気汚染の原因かつ有限であり、それが関係したことで生態系のバランスを崩してしまうと懸念されています。
発電施設の多くが化石燃料を利用しており、その燃料自体を使用しないことも社会全体としてCO2の削減に貢献できていると考えることができるでしょう。
そのほかバイオマスとなる資源が多く排出される地域に発電所を建設することで、地域の資源を無駄なく使用できるといったメリットもあります。(燃料輸送におけるCO2削減にもつながる)
もちろん、バイオマス発電を取り入れたからといって完璧なカーボンニュートラルにつながるとは考えてはなりません。
例えば樹木などの植物由来の燃料資源は有限であるため、資源用に成長させていく必要があるでしょう。
燃料資源が足りずに次々に樹木を伐採し続ければ、それらが吸収するCO2量が減少するため地球温暖化を促進させてしまう恐れがあります。
また、燃料資源の運搬や加工などさまざまな過程でCO2が排出されるため、それらをできる限り少なくする技術開発も急務です。
しかし、バイオマス発電は真のカーボンニュートラルを実現するポテンシャルを兼ね備えている発電方法であることは間違いありません。
今後、炭素循環の回転を速くする仕組みづくりの躍進、技術向上などによりバイオマスがカーボンニュートラルのモデルとなるように見守り続けていきましょう。
バイオマス発電でCO2削減に成功した実例
 バイオマス発電設備を導入した地方自治体は増加中であり、その中でもCO2削減を実現させている実例も少なくありません。
バイオマス発電設備を導入した地方自治体は増加中であり、その中でもCO2削減を実現させている実例も少なくありません。
まず、「脱炭素先行地域」に選定されている高知県梼原町の木質バイオマス発電です。
同町は木質バイオマスにおける地域循環利用の取り組みに力を入れており、化石燃料をバイオマスへとシフトさせた取り組みを行っています。
またバイオマス発電で地域創生を実現している岡山県真庭市ではCO2削減も成功させていることで話題です。
真庭バイオマス発電株式会社は、山林に放置されていた枝葉、今まで有償処分されていた未利用材をバイオマスとして燃料として発電に活用し、資源を有効活用させながらCO2削減を叶えました。
そのほか、青森県東北町はながいもの農業残渣を活用したバイオガスによる発電でCO2削減、福岡県みやま市は生ゴミを活用してC02の削減を実現させるなど、バイオマス発電の普及によって多くの自治体が真のカーボンニュートラルに向けた取り組みを成功させているのです。
まとめ
カーボンニュートラルは理想的な行動ですが、それを実現させるのは容易ではありません。
そんな中、バイオマス発電を取り入れた自治体などはすでにCO2削減を実現しており、これからさらにカーボンニュートラルを実現する上でバイオマス発電がスタンダードになってくることでしょう。
バイオマス発電の原理を理解すれば、カーボンニュートラルが叶えられることがわかるはずです。
まだまだ課題は山積ですが、バイオマス発電によるCO2削減効果を注視し続けていきましょう。
-
前の記事

地域経済とバイオマス発電の関係性!地方創生の新たな鍵に! 2025.09.23
-
次の記事

バイオマス発電所は進化している!安全対策とモニタリング体制の今を解説! 2025.09.24